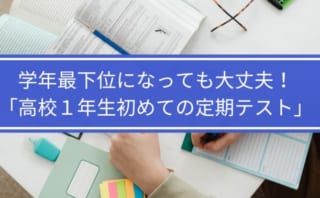娘は高校1年生の最初のテストでビリに近い成績を取ったことがあります。
学年最下位になっても大丈夫!!「高校1年生初めての定期テスト」
それはもう悲惨な点数を取りましたが、その後1年以上かけてコツコツ勉強を頑張った結果、少しずつ評定を上げて行くことができました。
高校1年生の評定平均は3.7(副教科だけは5が取れていました)
高校2年生の評定平均は4.7
高校3年生の評定平均は4.8(大学の一般入試を受けたので2学期末までの評定平均です)
高校3年間の総合平均は4.4となりました。
高校1年生の評定平均が3.7と高めだったのは、副教科だけ高得点を取れていたからです。
英語・数学・物理などの主要教科は全く授業について行けずボロボロな評定でスタートしました。

高校1年生の評定平均がもう少し高かったらなぁ…。

充分追い上げたよ!
入学当初は「高校を卒業できるのかな…?」と本気で心配するほど悲惨な点数を取っていた娘でしたので、2年生になって成績表を持ってくる度に「よく頑張ったね!」と褒めまくっていました。
さて校内の推薦選抜基準にも使われる「評定」ですが、娘の周りには平均4以上の友達がとても多くいました。

3年間の評定平均が4.9の友達もいたよ~!

理系で学年順位が常に2位の友達でした!
「もしかしたら、高校ではほとんどの生徒が4を貰えるのかな…?」と思うくらい多くいたので、実際どのくらいの生徒が評定4以上あるのかを調べてみることにしました。
ちなみに娘の通っていた高校では推薦を使って大学に進学する生徒はとても少なく、評定を甘く付けている様子はありませんでした。(一般入試に評定は関係ないので)
評定の付け方は高校によって全然違ってくるので、今回の記事の「評定平均4以上の生徒の割合」は娘の通っていた高校の場合となりますのでご了承ください。
※娘が通っていたのは偏差値60くらいの普通科の公立高校です。
評定平均4以上の生徒の割合
娘の通っていた高校では、評定平均4.0以上の生徒は驚くほどたくさんいる印象がありました。

私が入っていた部活では、9人中8人の評定平均が4.2以上だったよ。

今思えば成績優秀な子揃いだったね。
チームメイトもクラスメイトも、成績に関してはオープンな子ばかりで、お互いに成績表を机の上にばーん!と広げて見せ合いながら雑談している状態だったので、評定で嘘をついていないことは娘は確認済みでした。
そんなこともあり、娘は「高校では評定平均4以上あるのが当たり前なのかな?」と思っていたそうですが…
高校3年生で大学に提出する調査書が1通だけ余ったので中身の確認をしてみたところ、評定には基準が設けられていることが分かりました。
調査書の中身
調査書の中身についての記事はこちらです。
調査書の中に「学習成績概評」が記載されていますが、娘の通っていた高校ではA~Eまでの基準が設けられていました。
- A 学年順位 1~40番
- B 学年順位 41~140番
- C 学年順位 141~240番
- D 学年順位 241~最後まで
- E 0人(該当者なし)
娘はAに入っていましたが、3年間の評定平均が4以上だった友達は全員Aに入っていました。
B(学年順位が常に50番前後)の友達もいましたが、評定は3.9でギリギリ4に届いていませんでした。
この基準だけで考えると、評定平均4以上の生徒は最低でも学年に40人はいるのかな?という結果になりました。
国立教育政策研究所の成果報告書にもこのように書かれていました。↓
学習評価を実施する際に,評価目的に合わせて評価のための資料を入手することが必要になる。この項目は,どのような資料を評価資料とするかについての規定が設定されているかどうかについて尋ねたものである。結果は,全体の84.0%で規定を設けているとの回答となった。
引用:高等学校における学習の評価の実態把握と改善に関する研究
この文献を読んで、84%の高校で各評価結果の割合が設けられていることが分かりました。
例えば、評定5なら上位10%~20%まで。
評定4なら21%~40%まで。
※これは例えなので、高校によってパーセンテージは違います。
ほとんどの生徒に「評定平均4」が付けられている訳ではないことはこれで判明しました。

私の通っていた高校では、テストによって平均点プラス10点以上で4がついて、プラス20点以上で5がつくことが多かったよ。

提出物や授業態度も多少は評価に入っているよね。
大学の推薦がもらえる評定は?
娘の通っていた高校は「国公立信仰」が強かったので、学校からの推薦で私立大学に進学する生徒は、学年全体で10人くらいしかいませんでした。
生徒同士で「大学の推薦枠」を取り合うことはほとんどなかったため、娘の評定(4.4)があれば大阪の某有名私立大学の推薦が取れますよ、と担任の先生から言われました。

推薦が余ってる状態って今思うと贅沢だよね~。
ちなみに息子の通っている高校(偏差値55前後の普通科の高校)では推薦が取り合いです。

毎年学年の3分の1の生徒が推薦をもらって進学しているから、偏差値の高い大学から順番に取り合いだよ。
娘の持っていた評定4.4で余裕で取れると言われた大阪の有名私立大学の推薦ですが、息子の高校では争奪戦となっていて、最終的に評定4.9の先輩が勝ち取ったそうです。

3年間の平均評定が4.9って凄いね!
ところで息子の高校は評定は付け方が甘く、息子自身も平均点さえ取れれば4がつく教科もありました。

私の通っていた高校では考えられないよ…!
よく「評定いくつ以上なら大学の推薦がもらえますか?」という質問を見かけますが、結局のところ、高校によって評定の付け方は全く違うので「推薦をもらえる基準」については担任の先生に確認した方がいいです。

受験が終わった先輩に聞いても教えてもらえるよ。
「受験勉強」と「定期テスト」の勉強の大変さの違い
「一般受験組」と「推薦組」どちらが大変かと議論されることがよくあります。
娘は高校2~3年生は学年順位は常に1桁で、評定は4.7~4.8を維持し続けましたが、この評定を維持するために、いつも定期テスト3週間前から勉強を始めていました。

中間テストが始まる3週間前から次の期末テストが終わるまでは、帰宅後テレビを見ることもなく、家に帰って来てからはずっと勉強し続けている状態でした。
高い評定を維持するためには、3年間継続して勉強し続けなければなりません。
副教科など受験教科以外も勉強しなければならないので、それはもう大変です。
なので推薦をもらえる「評定の高い生徒」が並々ならぬ努力をして来たことは分かります。
それでも、推薦入試だと11月~12月には合否が決まります。
(娘の高校では推薦希望者の場合、高校3年生の1学期までの評定が使われたので、校内推薦は9月の初めに決まっていました)
年明けの1月~3月まで戦い続ける一般受験組の子たちの方がどうしたって長丁場になるので、どちらが大変かと言われれば100%「一般受験組」だと娘は言っています。

受験勉強が大変過ぎて、年末辺りから体調を崩す子が続出していたよ。
定期テストの勉強はどんなに長くても1カ月くらいなので、次のテストまで少し休憩することができるのですが、一般受験組は1年間ぶっ通しで勉強し続けることになります。
しかも合格の確約がされている「推薦」と違い、私立大学の場合は当日点一発勝負で「合格」の保証はどこにもない怖さとの戦いでもあります。

ストレスの面を考えても、一般受験組の方が間違いなく大変です。
ところで娘が通っていた高校では、国立大学に合格した生徒は評定4以上ある人がほとんどでした。
最後に
娘は大学受験は一般入試を受けたので、評定が役に立つことはありませんでした。

私が受けた大学は全て当日点一発勝負だったからね。
「評定」と言っても所詮は校内基準のものなので、「評定」を全く気にせず、一般入試に向けて受験勉強をがんばっている生徒もたくさんいました。

大学受験は全国の受験生との戦いだから、模試の偏差値を最優先に考える子が多かったよ。
高校の先生も高校3年生の2学期からは「赤点が回避できればいいから、定期テストより受験勉強を優先させるように」と言っていました。
娘も「最後の定期テストは最低限の点数しか取らない!」と宣言していました。
ところが「全力でテスト勉強する癖がついてて、どうしても定期テストの勉強の手を抜くことができなかった」と言って苦笑いしながら3学期の評定を見せてくれました。(4.8でした)
娘の「全力で勉強する癖」は大学、そして社会人になってからも健在です。

高校時代に定期テストで全力で勉強して高い評定を取っていた子は、大学に入学してからも全力で勉強を頑張ることができるというのは本当でした。
「学校の評定が低くて模試の偏差値が高い子」は、だんだん模試の偏差値が落ちて行く傾向にありますが…
「高校の評定が高くて模試の偏差値が低い子」は、最終的に偏差値を上げて行く子が多いと担任の先生から聞きました。

受験勉強と学校の勉強(定期テスト)どっちも頑張ることが大事だよ。
残っていくのは「本物」だけです
授業だけでは理解の怪しい分野の「観る必要がある部分だけ」スタディサプリをピンポイントに活用することをおすすめします!
娘は古典の講座が分かりやすいと言っていて、古典だけは常に学年一位を取っていました。
娘は中学一年生から高校三年生の大学受験が終わるまで、「学校の教科書、参考書」と併用してスタディサプリを使っていました。